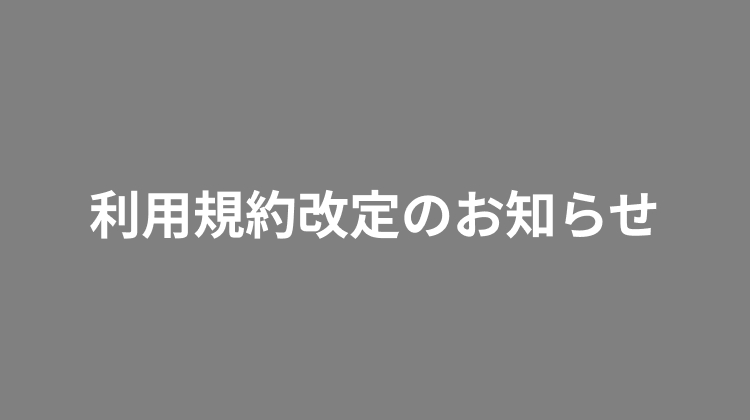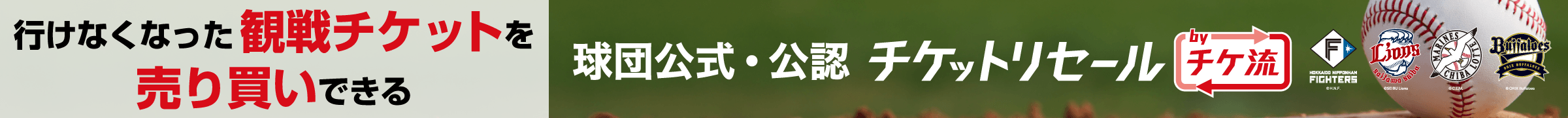第100回全国高等学校野球選手権記念大会が閉幕した。今年も甲子園で高校野球の頂点を巡る戦いから、多くの新たな物語が紡がれている。夢見た舞台へ辿り着くために、球児たちはどれだけの鍛錬、挑戦、葛藤を積み重ねているのだろうか。現役プロ野球選手の高校時代を振り返る連載第12回は、いくつもの壁を乗り越えてきた菊池雄星投手(埼玉西武)。しなる左腕から繰り出す快速球で甲子園を沸かせ、ひたむきな姿勢がファンの胸を打った。真っ直ぐな心で野球と向き合う姿は、今もあの頃と変わらない。自身を奮い立たせたライバルたちとの名勝負数え唄は、舞台をプロの世界に移して続いている。
現在もしのぎを削る「91年世代」
世代別でプロ野球選手が語られるようになったのは「98年世代」からだろう。松坂大輔投手(中日)を筆頭格として、和田毅投手(福岡ソフトバンク)、杉内俊哉投手(巨人)、村田修一選手(元巨人)、古木克明選手(元横浜)など、1998年夏の全国高等学校野球選手大会で甲子園を沸かせた選手たちが、高卒、大卒、社会人と経由は異なるものの、プロに入ってからも注目を浴び続けたことで「松坂世代」という呼び名が有名になった。
それ以後では、甲子園で対戦してそのままプロに入ってもライバル関係にあったケースがそう多いわけではない。2006年の「田中(将大/ヤンキース)・斎藤(佑樹/北海道日本ハム)世代」は豊作として知られるが、高校時代から対戦してライバルであり続けたというわけではない。田中投手と前田健太投手(ドジャース)は、高校でもプロでも対戦はなかったし、坂本勇人選手(巨人)も選抜高等学校野球大会には出場しているが、3投手との対戦はない。
そういった視点で見ていくと、最大派閥になるのが1991年生まれの「筒香(嘉智/横浜DeNA)・菊池(雄星/埼玉西武)世代」だ。高校時代に2人の直接対決はないが、今村猛投手(広島)、大瀬良大地投手(広島)、今宮健太選手(福岡ソフトバンク)、秋山拓巳投手(阪神)、岡田俊哉投手(中日)、堂林翔太選手(広島)、原口文仁選手(阪神)、岡大海選手(千葉ロッテ)、西浦直亨選手(東京ヤクルト)ら、なかなかの面子が甲子園出場を果たしているのだ。
菊池投手は今宮選手、今村投手、堂林選手と甲子園で対戦している。国民体育大会では秋山投手、原口選手らと友人になったと語っているし、今宮選手は秋山投手と対戦し、代表では岡田投手とともに日の丸入りを果たした。
「筒香や秋山、原口など高校時代に話したことのある選手がみんなプロに入っている。同世代の存在は刺激になりましたね」
高校時代の思い出をそう語るのは、埼玉西武のエース・菊池投手だ。彼ほど、甲子園のライバルたちに刺激を受け、成長した選手はいないと言っていい。
そもそも、91年世代でイの一番に脚光を浴びたのが菊池投手だった。高校1年夏、甲子園出場を果たすと、5回からマウンドに上がり1失点の好投を見せた。ストレートの球速は145キロを計測し、「岩手に怪物あり」の衝撃的なデビューを飾った。
「1年の時の甲子園はあっという間に終わりました。甲子園に入って『でけぇ』と思ったのが第一印象でした。1回戦で負けたんですけど、最後のイニングにマウンドに上がるとき、甲子園に来るのはこれが最後かもしれないと思って、全力で投げたのを覚えています」
そんな衝撃デビューは彼の名前を一躍スターダムにのし上げ、岩手県で菊池投手を知らない人はいないほど有名にした。そして、同時にそのプレッシャーに押しつぶされた。1年夏は先輩に連れて行ってもらった甲子園で、ただただ腕を振るだけで良かった。しかし、2年になってからは常に注目を浴びながらチームを引っ張らないといけないことになり、不安定な時期を過ごしたのだ。
力んでフォームはバラバラになり、あの衝撃デビューのときのようなストレートは鳴りを潜めた。2年春、夏ともに、甲子園出場を逃した。そんな折に、将来のスター候補性として甲子園で活躍したのが筒香選手達だった。菊池投手の回想だ。
「『1年で甲子園で投げた菊池雄星だ』という目で見られるようになって、力みまくってしまいました。フォームがばらばらになって135キロしか出なくなって、ストライクも入らない。1年間はそういう状態が続きました。他の同級生たちがどんどん有名になって焦りました。岡田君や今村君、筒香君が2年生夏の甲子園で活躍していたのを見て、それまでに持っていた自信がなくなりました」
同世代を意識したからこそ、彼の中での焦りにつながったのかもしれない。しかし、それは後に強さとなる。
成熟しても、心は野球小僧のままで
翌年のセンバツに出場を果たすと1回戦の鵡川高校戦では9回1死までノーヒットノーランの衝撃的な“甲子園復帰”を見せると、決勝まで勝ち上がった。ともに県勢初優勝を懸けて相まみえた清峰高校・今村投手との決勝戦はセンバツ球史に残る投手戦だった。
結果は0対1で敗戦。最後の打者が外野フライに倒れて準優勝に終わり、ゲームセットの瞬間に走者だった菊池投手が名残惜しそうにしてホームベースを踏んでいたのは印象的だった。「神様が日本一にはまだ早いと言っているのだと思います」と菊池投手が語った言葉は、夏へのさらなる成長を予感させた。
そして、夏、菊池投手は甲子園に戻ってきた。もっとも、ここに来るまでは、世間からの注目を浴び続けたのだが、1年夏とはまた違う甲子園の偉大さに気づいたと振り返っている。
「僕らはただ必死にやっていただけだったんですけど、岩手県での反響がすごかった。それまで高校野球に関心がなかったおじいちゃん、おばあちゃんも野球が好きになってくれて、『感動したよ』って言ってくれた。練習試合では、以前までは父母の方しか観戦に来なかったのに、学校のグラウンドが満杯になった。僕らが取り組んでいたことが中学校で流行ったり、そういうのはうれしかったですね」
夏の1回戦は、長崎県大会で今村投手のいる清峰高校を破った長崎日大高校だった。エースを務めていたのが、大瀬良投手で2人は投げ合ったのだった。
準々決勝の明豊高校戦。菊池投手は打者走者として1塁を駆け抜けようとしたときに、相手野手と衝突。この大会は最後まで全力を出し切ることはできなかった。準決勝で堂林選手のいた中京大中京高校に敗退し、菊池投手の甲子園は終わった。
1年夏に甲子園に出場し、脚光を浴びた。紆余曲折があり、菊池投手を奮い立たせてくれたのはライバルたちの存在で、彼の高校3年間は甲子園を軸にして展開された。菊池投手は甲子園の思い出をこう振り返っている。
「甲子園によって注目してもらった3年間でした。いいことばかりじゃなかったのかもしれないけど、皆さんに見てもらって、野球選手として名前を知ってもらえた。僕は甲子園に感謝しています」
現在、チームのエースとして活躍中の菊池投手は、夏になると、時間があればロッカールームで高校野球をチェックしているという。
「〇〇くん、トレーニング変えたら、150キロ出せますね」
この夏、そんな会話を楽しそうにする菊池投手がいた。
【高校野球企画】Youthful Days ~まだ見ぬ自分を追いかけて~
vol.1 浅村栄斗選手[埼玉西武]
vol.2 上林誠知選手[福岡ソフトバンク]
vol.3 金子千尋投手[オリックス]
vol.4 平沢大河選手[千葉ロッテ]
vol.5 中田翔選手[北海道日本ハム]
vol.6 松井裕樹投手[東北楽天]
vol.7 西川遥輝選手[北海道日本ハム]
vol.8 T-岡田選手選手[オリックス]
vol.9 田村龍弘選手[千葉ロッテ]
vol.10 今宮健太選手[福岡ソフトバンク]
vol.11 今江年晶選手[東北楽天]


![【高校野球企画】Youthful Days ~まだ見ぬ自分を追いかけて~ vol.11 今江年晶選手[東北楽天]](https://media.insight.pacificleague.com/PI0AGDa8spaeFi1FnyL9g7dqldFCmSSJ28EGYAJB.jpg)
![【高校野球企画】Youthful Days ~まだ見ぬ自分を追いかけて~ vol.10 今宮健太選手[福岡ソフトバンク]](https://media.insight.pacificleague.com/9nlS81tGImRaxcLqr56TplZVHlnwIcyBe85hugut.jpg)
![【高校野球企画】Youthful Days ~まだ見ぬ自分を追いかけて~ vol.9 田村龍弘選手[千葉ロッテ]](https://media.insight.pacificleague.com/KSYpDQ5cstmUJXP7Bx0KTbEHkuQicY3dCLAaVr5n.jpg)
![【高校野球企画】Youthful Days ~まだ見ぬ自分を追いかけて~ vol.8 T-岡田選手[オリックス]](https://media.insight.pacificleague.com/1p7ud2kD2oE4tWWHyCLw3PBOdMN7MtAmcHPT1f8F.jpg)