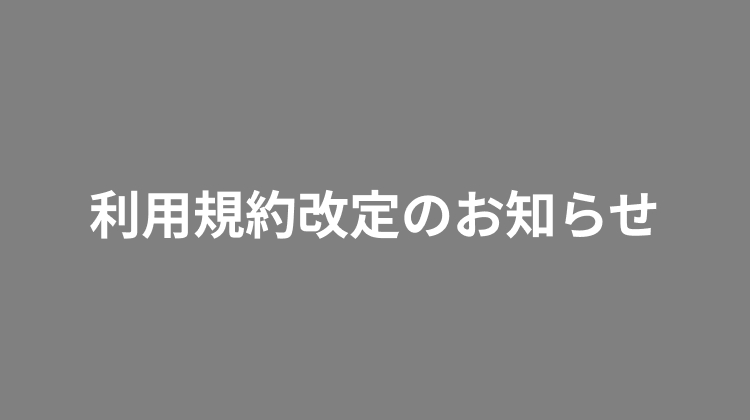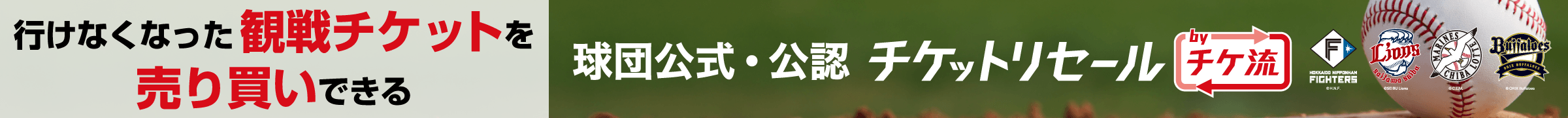大谷翔平選手がマイク・トラウト選手を抑えたその瞬間。マウンド付近にはバッテリーを中心に歓喜の輪ができ、それが解けるとコーチや監督らと熱い抱擁を交わした。
日本列島を熱狂の渦に包んだ歴史的瞬間だが、その輪には加わらず三塁側スタンドから見守っていた“チーム侍ジャパン”がいたことも、私たちは知っておきたい。
これは、ベンチ外や球場外で奮闘した、侍ジャパンの“頭脳”ーーデータアナリスト3名の話だ。
「データアナリスト」という仕事
野球という競技は、選手個人の心技体の鍛錬の賜物であることは言うまでもないが、同時に非常に高度な情報戦でもある。大切なのはその情報の生かし方。データを数字として表面的に見るのではなく、データが持つ意味を咀嚼、言語化し、プロチームに対して適切なアドバイスをするのが、〈データスタジアム株式会社〉のアナリストチームだ。
山田隼哉さん、佐藤優太さん、河野岳志さんのアナリスト3名は、普段は同社の野球ビジネスにまつわる仕事として、球団から依頼を受けてデータ分析やレポート制作を行ったり、メディアに向けて寄稿やデータ提供を行っている。



特にスコアラーやアナリストという肩書きの球団スタッフと関わることが多く、球団が持つデータと独自に収集したデータを組み合わせ、“意味のある形”にして戻すということがメインの仕事だ。1枚のレポートにすることもあれば、BIツールを使って球団内で自由に見られるように提供することもあるという。
「提供して終わりではなく、出てきた数値に対してどのように読み解くかということが大事なので、球団の方と相談しながら意思決定につなげていくようにしています。球団内にもアナリストはいますが、まかないきれない部分をサポートしたり、トラッキングデータやセイバーメトリクスなど、より専門的な知見が求められる部分についてはこちらから助言や提案をすることもあります」(山田さん)
そんなデータ分析のプロ集団の、さらなる精鋭部隊がトップチームに加わるようになったのは、北京五輪予選(2007年)からだった。担当者は代々引き継がれ、山田さんは2014年、佐藤さんは2021年、河野さんは2022年から一員となっている。
「選手選考のための資料作成から始動し、海外リーグのデータや映像を集め、チームが活用できるレポートの状態に仕上げて提供します。昔は分析するための素材を整理して提供するまでが主な任務でしたが、近年の大会では、分析して、現場に落とし込むところまで範囲を拡大して担うようになりました」(山田さん)
過去の国際大会では2名の派遣だったが、今回は山田さん、佐藤さん、河野さんの3名が代表合宿からチームに帯同した。山田さんと河野さんが野手担当として相手のピッチャーを分析し、侍ジャパンのバッターに対して情報を提供。山田さんは同時にNPBとの調整や全体のタスク管理、また最も大事な仕事として、試合前の野手ミーティングで相手投手の特徴をプレゼン形式で伝える役割を担った。そして佐藤さんはバッテリー担当。相手のバッターを分析し、主にキャッチャーに向けて情報を伝達した。
リーダーである山田さんは34歳、佐藤さんは29歳、河野さんは26歳と選手たちと同年代である。体育大で硬式野球をやってきた河野さんもいるが、山田さんと佐藤さんは野球のプレイヤー経験としてはそれぞれ高校と中学までだという。だからこそ選手の技術やコンディションとは一線を引く、データに基づく客観的な提言にコーチも選手も信用があったのだろう。
データがない? 初対戦のチームはどう対策したか

実力差はあるだろうと予想できるとはいえ、初対戦のチームはやはり不気味なものはある。
今WBCの東京プールでは、対戦実績やプロリーグの情報がなくデータが極端に少ないチームもあった。基本的に映像など何もない場合は、ある程度割り切って選手に任せていたという。
「ただ、何もないと選手としても不安になると思うので、わかる範囲でのデータは提供するようにしていました。WBCの予選に出ていたチームは、そこでの数試合のデータと映像をもとに、例えば持ち球、軌道、割合などの情報を基本的なピッチャーのイメージとして把握できるようなレポートをつくりました。どれくらいのレベル感なのかということを首脳陣の方々も気にされていたと思うので、限られた素材のなかから、嘘はつかず言えることは言うようにしていましたね」(山田さん)
反対にMLBやKBO、NPBに所属する相手選手の場合は、シーズンの数字からかなりのデータを得られるが、直近の傾向も大事にする。両方を並べながら、どちらを首脳陣や選手に伝えていくかを考えた。
だが、こうして山田さんたちが叩き出したデータだけでなく、実際に対戦した感触や自らが保有する“生”のデータをMLB組の選手らは持っていた。ダルビッシュ投手らを中心とするMLBの選手らが当然のようにデータを駆使する様子に、時に3人はプレッシャーを感じることになる。
「韓国戦前のバッテリーミーティングにダルビッシュ投手が同席されたことがあって、タブレットでデータを見ながら対戦選手の話をされていましたが、ちょっとレベルが違うなと感じました。データに対するリテラシーや、活用の仕方、どこを調べればどういったデータが出せるといったことが、習慣から身に付いているんだろうなと思いました」(佐藤さん)
「ダルビッシュ投手は大会前からそういうデータを見ていて、韓国代表にいるMLB選手の分析は終わっていると言っていましたね」(山田さん)
「それを見た時に、選手から何か聞かれてもちゃんと答えられる準備をしていかないとなと思いました」(佐藤さん)
「そういう意味では我々アナリストも、選手たちに育てられているというか、成長を促される存在なので、選手のリテラシーが上がるということは、我々はもっと上をいかなければならないというプレッシャーはあります」(山田さん)
いざ、マイアミへ。膨大なデータと日夜戦う
準決勝、舞台をマイアミに移してからは「食事が合わなくてキツかった」と佐藤さんが回顧するように、慣れない環境との戦いもありつつ、今度は膨大にあるデータをどう処理するかの作業に追われた。
「例えば去年のデータをまるごと使うのか、後半だけ使うのか、今大会の数試合だけを使うのかということが選択肢としてありました。あとはピッチャーのデータで感じていることとして、シーズン中の球種の割合はそんなに当てにならないと思っています。国際大会になれば場面の重要度もキャッチャーも変わりますし。そこはミーティングでどう伝えるか考えて、あくまで去年のシーズンの傾向としてはこうであるけれども、絶対解ではないということは工夫して伝えたつもりです」(山田さん)
実際にメキシコのサンドバル(エンゼルス)が大谷選手にチェンジアップを何球か投げたが、シーズン中の傾向からすると左バッターにチェンジアップを投げるのはほとんどないことだった。こういったことを踏まえ「シーズン中の割合は絶対ではない」という伝え方は大事なのだと話す。
「もう一歩踏み込むと、シーズン中にあまり投げていない球種というのは、投手にとってそれだけ自信がない球種でもあるので、そこまでクオリティは高くないボールだったりします。そのため、チェンジアップをケアする必要はないよと伝えても、意外と問題にならないことも多いです」(山田さん)
そのため、情報の伝え方には気を遣ったという。3人に共通していたことは、“直感的に選手たちが理解できること”。
「おそらくそれを気にしていないアナリストはいないと思います。いろいろな可能性を言い出すと選手も迷ってしまうので、敢えて言わないようにしたり」(山田さん)
「例えば私のスカウティングレポートでは、詳細なデータをなるべく直感的に理解できるように表現を工夫しました。そうなるとどうしても簡素なデータになってしまいがちですが、データの正しさとわかりやすさを両立させることは、今回に限らず普段から気にしています」(佐藤さん)
「特に海外の投手は日本と比べてクイックをあまりしないので、スカウティングレポートではクイックをするピッチャーかどうかを一目見てわかるように気を付けていました」(河野さん)

アナリストの仕事としては、試合前にホテルでミーティングをして選手を送り出して終わる。ベンチ入りはできないため、東京ドームではホテルから、ローンデポ・パークでは客席から応援した。メキシコ戦のあの村上宗隆選手のサヨナラタイムリーは、アナリストの頭脳から予測できたのだろうか。
「正直、レフトに打球が飛ぶたびにアロサレーナ(レイズ)がキャッチして、心が折れかけていて(笑)。ただ、よく中南米のチームにありがちなこととして、リリーバーになると少しレベルが落ちるというのがあったので、8回表に5対3とリードを広げられた時点では、まだいけると思っていました。クローザーのガイエゴス(カージナルス)は、メジャーではかなりレベルの高い成績を残している選手ですが、球種が少ない。
選手がどう感じるかはわからないですが、個人的な感覚としては、チャンスはあると感じていました。持ち球が少ないと、バッターとしても初めて対戦するピッチャーの球種が絞りやすいというだけで大きいので。実際、村上選手が打った瞬間は泣きそうでした」(山田さん)
興奮冷めやらぬまま、20時間後、決勝のアメリカ戦を迎えることとなった。これが本当に最後の試合、最後の仕事だ。
「アメリカ戦はスケジュールがタイトで、バッテリーミーティングも軽めでした。どちらかというと、ここまで来たら自分たちのいいところを出していこうという、人事を尽くして天命を待つ雰囲気でした。いよいよこれで終わるんだという感じがしたのは覚えています」(佐藤さん)
「あまり決勝の試合前までの記憶がなくて(笑)。メキシコ戦が終わった後に決勝のミーティング映像とかをつくらなければならなくて、わりと遅くまでやっていたので、寝不足と、試合の興奮であまり覚えていないです。アメリカ戦は、球場に入ってからはアナリストとしての仕事は終わっていたので、あとは試合を楽しむだけという感じでした」(河野さん)

筆者も現地で戦況を見守っていたが、地響きのようなUSAコールで、東京プールを懐かしく感じさせるほどの完全アウェーだった。ビハインドに苛立った観客の、怒号にも悲鳴にも近い声援を背に受け「圧がすごかった」「これまでに経験したことがないほど異質だった」と3人は振り返る。そして冒頭のシーンだ。

MLBでトップクラスに活躍をしているダルビッシュ投手や大谷選手が、データを活用して自分のパフォーマンスアップや相手の分析をしていることに、NPBの選手が影響を受けて帰ってきたということは、日本プロ野球界にとって金メダル級の“おみやげ”だっただろう。
「これからもモヤモヤをずっと抱えながらやっていく仕事なんだろうな」
あの熱狂から数カ月。関連映画も公開されるなど余韻もあるが、今3人があらためて思うこととは。
「昨年11月のオーストラリアとの強化試合が初めての侍ジャパン帯同で、大会を通してアナリストを務めたのは今回が初めて。そこで優勝できたというのは本当に今までの人生の中でも一番の経験だったと思います。ダルビッシュ投手をはじめとしたトップ選手だけがデータを活用するのではなく、アマチュアの選手も同じようにデータ活用ができるように、今後の自分の仕事を頑張っていきたいと思いました」(河野さん)
「優勝の瞬間を見たときに、これからの人生を含めてこれ以上ドラマチックな出来事を目撃することはないだろうと直感的に思ってしまったのですが、これを超えられないにしても、次回の大会も金メダルを狙いにいかなければならないので、ハードルがすごく上がったなと思います。
今回はダルビッシュ投手などのプレイヤーがどうデータを活用しているかや、一緒に帯同していたMLBのアナリストからメジャーリーグでどういうアプリを使って、どういうデータを見て、どう選手を支えているかを知れたので、自分の中での伝え方や分析手法などの知見の幅が広がった実感があります。
それに、自分のつくったスカウティングレポートを、実際に現場で活用してもらえたというところも自信になり、次回大会に向けての決意を新たにした大会でした」(佐藤さん)
「大勢の裏方さんがいて、皆さんそれぞれ大変ななかで世界一になれたのはひとつの成果だと思います。一方で、果たしてどれだけ貢献できたんだろうということに対するモヤモヤした気持ちもあります。あの場面ではこういうことができたんじゃないかとか、あの情報はこういうふうに伝えたほうがよかったんじゃないかとか。正解はないですし、アナリストがチームにどれだけ貢献したかは定量化できないので。
それは過去の大会でも感じたことで、WBCで優勝してもなお感じるということは、おそらくこれからもそのモヤモヤをずっと抱えながらやっていく仕事なんだろうな、と。そして選手たちもレベルアップしていくので、我々も置いて行かれないようにパワーアップし続けなければいけないということを感じた大会でした。
個人としてはトップチームの担当を9年間務めましたので、今後は現場の最前線に立つよりも佐藤、河野に続く次世代のアナリストを育てないといけないと思っています。WBC前回大会の準決勝敗退も、プレミア12の負けも優勝も、オリンピック金メダルも経験したし、今回は悲願の世界一ということで。(有終の美?)いや、勝ち逃げですね(笑)」(山田さん)
文・海老原 悠