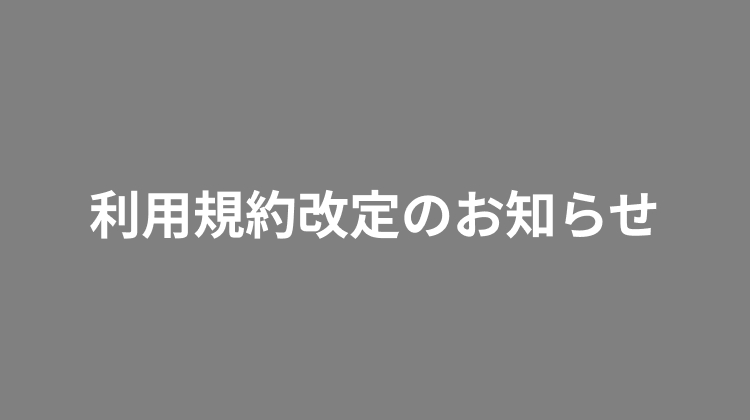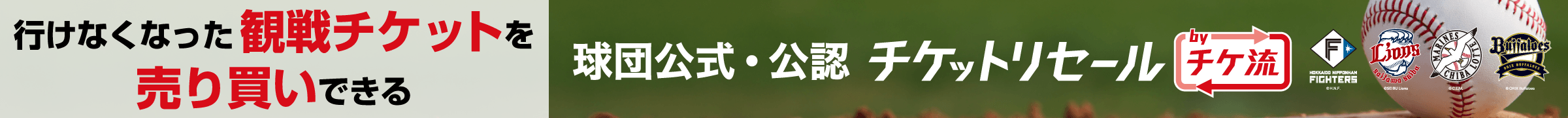甲子園では本塁打の減少が話題になったが、プロの世界は別?
2年ぶりに開催された春のセンバツ高校野球は東海大相模高校の優勝という結果で幕を閉じた。この大会では大会初本塁打がなかなか生まれず、大会5日目、通算13試合目にようやく初めての柵越えが飛び出した。昨年の交流試合から続く甲子園での本塁打減は、傾向として如実に現れつつある。
しかし、プロ野球の世界では話は別のようだ。パ・リーグにおいては、各チームが開幕カードを消化した時点で、合計18本のホームランが出た。ちょうど1試合に2本の割合という派手なスタートを切ると、2カード目の終了時点でも17試合で30本と、開幕直後は各地で本塁打が飛び交っていた。
翻って昨季の数字を見てみると、リーグ全体の本塁打数は直近の5年間で最少だった。それだけに、開幕直後に起こった本塁打の急増は目を見張るものがある。今回はその内訳や昨季との比較を行い、その理由についても考えていきたい。
※数字は4月1日時点の成績
数字としては直近5年間で最少だったが、違った観点から見てみると……
まずは、直近5年間のパ・リーグにおける、年度別のリーグ全体の本塁打数を確認しよう。

やや本塁打数が少なかった2016年に比べ、2017年には前年比で150本以上も増加。2018年の本塁打数はさらに74本伸びており、2019年も前年同様に850本を超すホームランが飛び交った。全体的に本塁打が量産される傾向にあった中で、先述の通り、2020年は614本と過去5年間で最小の数字となっていた。
ただ、2020年は試合数が120試合に削減されたことに加え、1日に公式戦6試合が開催される交流戦が行われなかったことも影響しているだろう。2020年の数字を143試合に換算した場合の本塁打数は、約732本。ペースとしては、2016年の数字を100本以上、上回る計算になる。
また、交流戦の未開催によって全試合がパ・リーグのチーム同士での試合となったことも影響してか、1試合平均での本塁打数は2017年を上回る数字となっていた。試合数が再び143試合に戻る予定となっている2021年は、2019年以前に近い、あるいはそれを上回る本塁打数が記録される可能性もあるかもしれない。
2020年に比べて、今季は「どこからでも本塁打が飛び出す」傾向にある
次に、昨季の傾向について見るために、2020年の本塁打数ランキング上位10名の顔ぶれと、その本塁打数を見ていきたい。

上位10名だけで228本のホームランが記録されただけでなく、浅村選手、中田選手、柳田選手という上位3名の選手だけで、合計92本の本塁打が記録されていた。リーグ全体の本塁打数が851本だったことを考えると、全体の本塁打数のうち、実に26.7%が、本塁打ランキング上位10名の選手だけで占められていた計算になる。
しかし、今季の開幕から2カードが終了した時点で本塁打を記録した選手の顔ぶれを確認すると、その傾向の違いが如実に見て取れる。

昨季の本塁打数がリーグ2位だった中田翔選手は、6試合終了時点で1本もホームランを記録していない。また、昨季の本塁打王である浅村選手もまだ1本と、実績ある長距離砲の多くがまだ量産体制には至っていない。それにもかかわらず、リーグ全体の本塁打数は増加しているという事実が、「どこからでも本塁打が飛び出す」という状況を端的に示している。
また、開幕直後にハイペースで本塁打を量産する選手もこの段階では存在せず、多くの選手が満遍なく本塁打を記録していた点も特徴的だ。すなわち、リーグ全体の本塁打増という傾向は、特定の選手の覚醒によってもたらされているわけではないということでもある。
主力から伏兵まで、多くの捕手が開幕直後から豪快な一発を記録
ポジションという観点でいえば、開幕カードで記録された18本のホームランのうち、7本が捕手登録の選手によって記録されたように、捕手による本塁打が多い点も興味深い。開幕3戦目までに太田光選手と森友哉選手が2本の本塁打を記録しただけでなく、頓宮裕真選手、吉田裕太選手、甲斐拓也選手といった捕手登録の選手たちが、3戦目までに早くも本塁打を記録している。
一般的に、捕手というポジションは守備の負担が大きく、打撃面で結果を残すのは難しいとされている。ただ、それぞれ2度のベストナイン受賞歴を持つ森選手と甲斐選手をはじめ、頓宮選手も昨季はわずか12試合で2本塁打、打率.313と打撃面で優れた才能を示しており、パンチ力のある捕手は各球団で増加傾向にある。そして、昨季17本塁打の栗原選手は登録ポジションこそ捕手ながら、外野手や一塁手としての出場が大半となっている。
その一方で、昨季は67試合で2本塁打、打率.200と打撃面では苦戦した太田選手が早くも昨季の本塁打数に並び、昨季までの7年間で通算本塁打が8本だった吉田裕太選手も、オープン戦での好調を開幕戦で結果につなげた。下位打線や代打で出場する捕手に意外性のある一発が生まれている点が、今季の流れを象徴している面もあるだろう。
先発が投げているうちに捉えようという意識が、多くの本塁打を生む?
最後に、このような傾向が生まれている理由の一端を示す数字を。各選手が本塁打を放った投手の内訳は、先発からが23本、リリーフからが7本となっている。その一方で、先発投手相手に7回以降に記録された本塁打は開幕戦で頓宮選手が放った1本のみと、先発から放ったホームランのうち、ほぼすべてが6回までに記録された本塁打となっていた点も興味深いところだ。
こういった数字の要因となるのが、今季の試合は最長で9イニングまでという規定だ。最終回から逆算した投手起用がより行いやすくなったというだけでなく、先発投手から早めにリリーフ陣へとスイッチすることも、これまでよりも容易となっている。
すなわち、ベンチから一定以上の信頼を得ているリリーフ投手が登板する割合が、例年以上に高くなる公算が大きいということだ。そのため、先発投手が投げているうちに点を取るために、試合前に組み立てる相手投手攻略のプランがより重要さを増してくる。先発投手に対して、打順の上位・下位に関係なく強いスイングが目立つ点や、配球の読みに長けた捕手登録の選手に本塁打が多い点も、こういった要素から一定の説明がつけられる。
本塁打の増加は開幕直後の一過性のものか、それとも
昨季は120試合の短縮シーズンということもあり、従来とはさまざまな面で異なる傾向を示したシーズンとなった。今季は試合数が143試合に戻ることが予定されているが、今回取り上げた本塁打数の増加をはじめ、昨季とはまた違ったかたちで、通常のシーズンとは違う傾向を示す1年となるかもしれない。
また、各チームが多くの本塁打を記録している中で、北海道日本ハムだけが6試合終了時点でチーム本塁打が0本と、やや出遅れている点は気になるところ。昨季の89本塁打はリーグ最下位ではあったが、同4位タイの千葉ロッテとオリックスとの差はわずか1本。昨季31本塁打の中田翔選手も擁するだけに、ファイターズ打線にエンジンがかかってくれば、リーグ全体の本塁打数も、さらに増加する可能性はありそうだ。
開幕直後に巻き起こったホームランの急増は一過性のものとして終わるか、あるいはこのまま本塁打増加の傾向は続くのか。今季の傾向の変化を端的に示す「野球の華」に、今後も注目していく価値は大いにありそうだ。
文・望月遼太