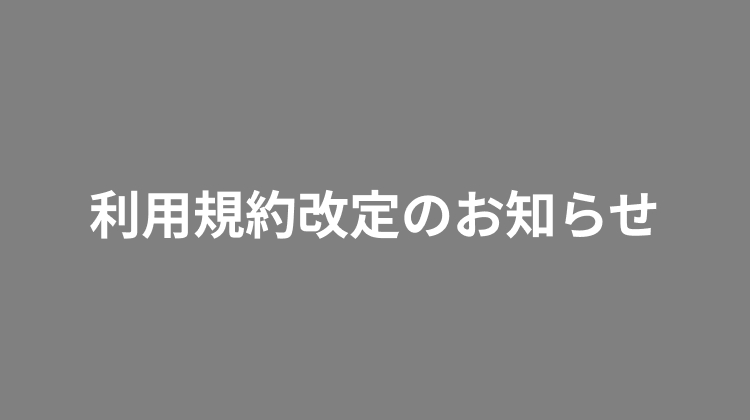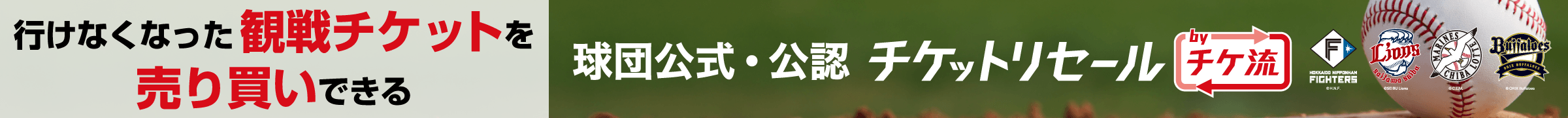高卒5年というわずかな期間で日本球界の常識を覆してきた男が、ついに海の向こう、プロ野球世界最高峰の舞台に飛び立つ。11月11日、北海道日本ハムの大谷翔平選手はメジャーリーグに挑戦する意向を表明。そして12月9日(日本時間10日)、ロサンゼルス・エンゼルスの本拠地で入団会見を行った。
花巻東高校時代、投手としてアマチュア最速の160キロをマークし、同時に打者としても非凡な才能を見せ付け、大きな注目を浴びた大谷選手。とはいえ、アマチュア時代に投打で実績を残したプロ野球選手はそう珍しいものではなかった。大谷選手が「二刀流」と称されながら北海道日本ハムへ入団したとき、いずれは投手か野手のどちらかに専念するだろうという意見が圧倒的に多かったことは、当時を知らないファンでも容易に想像がつくだろう。
しかし、栗山監督率いる北海道日本ハムの環境、大谷選手自身の類い稀な能力は、日本球界では前例のない「二刀流」の実現を可能にしていく。ルーキーイヤーの2013年は、8番・右翼として開幕スタメン入りし、いきなりマルチ安打を放つ。投手として登板した際には157キロを計測し、3勝を挙げた。2年目の2014年には、早くも日本人最速となる162キロを叩き出し、11勝をマーク。打者としても10本のアーチを描き、日本球界では史上初の「2桁勝利・2桁本塁打」の快挙を達成する。2015年には最多勝、最優秀防御率、最高勝率の投手3冠を獲得し、高卒3年目にして球界を代表するエースにまで上り詰めた。
ただこの頃、代名詞である「二刀流」に対して、再び疑問の声が上がる。大谷選手の打者としての能力を侮っていたからではない。あまりに投手としての能力が突出しているために、2倍の負担を引き受ける「二刀流」ではなく「投」を極めることが、大谷選手自身、ひいては日本球界の未来のためではないかという論調だった。この年のオフに行われた「2015 WBSC プレミア12」における圧巻の投球も、その意見を後押ししただろう。
しかし昨季、大谷選手が所属する北海道日本ハムは、福岡ソフトバンクとの11.5ゲーム差をひっくり返してパ・リーグを制覇すると、そのままの勢いで日本一の頂に駆け上がった。そして多くの魅力を備えたチームの中、いつも大谷選手が投打の中心に仁王立ちしていたことは、まだ多くのファンの記憶に新しいだろう。
プロ野球史上初の1番・投手による先頭打者本塁打。高卒2年目から3年連続2桁勝利。投げては日本球界最速の165キロを叩き出し、打っては22本の美しいアーチを描く。パ・リーグを制したその日も最後までマウンドを守り、日本シリーズでは芸術的なまでの悪球打ちを披露し、最終的に指名打者・投手部門でともにベストナイン、リーグMVPに輝いた。
「二刀流」の実現を疑問視する声、投手としての欠点を指摘する声、打者としての才能こそを評価し、「一刀」を極めることを勧める声。大谷選手はこの激動の5年間で、その全てを自身が秘める可能性への称賛に変えてみせた。野球の歴史は長いが、大谷翔平という稀有な選手の存在により、我々は何度歴史的瞬間を目撃したのか。もはや枚挙に暇がないほどだろう。
11月の会見では、「ファイターズに入ってよかった。それは一生思う」と語った大谷選手。その気持ちは、「4番・投手」として出場した今季最終戦において、完封勝利という最高の形でも示した。言葉だけではなく、結果を伴わせた形で記念すべきマウンドを締めたのも、大谷選手らしいと言えるのではないだろうか。
12月9日(日本時間10日)にエンゼル・スタジアムで行った入団会見でも、大谷選手は移籍に際して奔走した代理人、自身の獲得に動いた他の球団に対する感謝を伝えるために言葉を尽くした。その謙虚な姿勢、聡明な好青年としての姿は、野球ファンなら幾度となく目にしてきたものではあるだろう。
しかし、「野球をやっている以上は、一番の選手になりたいと思うのが普通。いろんな方に『彼が一番だ』って言ってもらえることが幸せ。そういう選手を目指していきたい」と話す姿は、「謙虚」「好青年」といった形容に似つかわしくない苛烈さを秘める。「世界で一番になる」ということは、自身の上には誰も立たせないということだ。これから待ち受ける多くの競争に、全て打ち勝っていくということだ。それはきっと、何を差し置いても過酷な道を突き進む覚悟と、計り知れないほど強靭な意志がなければ成し得ないことだろう。
エンゼルスの一員として、大谷選手がメジャーリーグの舞台で「二刀流」に挑むのかどうかはまだ分からない。ただ、この若者に何度も想像を超えられてきた我々は、何も始まっていない段階から、彼の可能性の何一つとして否定するべきではないだろう。しかし、周囲から「そんなことはできない」と侮られると、余計に燃え上がる選手なのだ。次は海の向こう、うんと目の肥えた人々の常識を変えてくれることを期待しながら、ただ今は、ついに夢への一歩を踏み出したその背中にエールを送りたい。
記事提供:![]()
特集