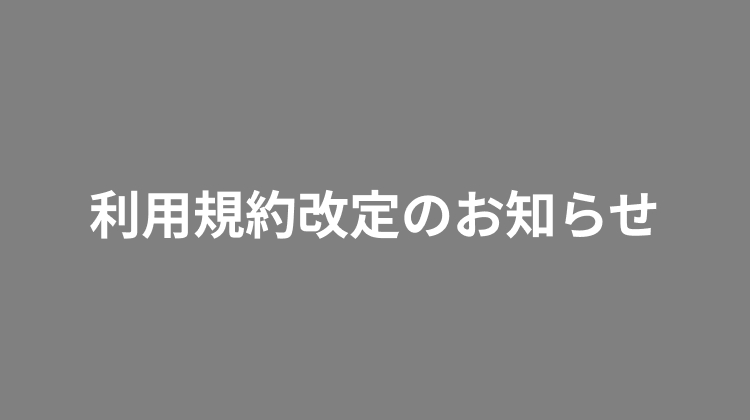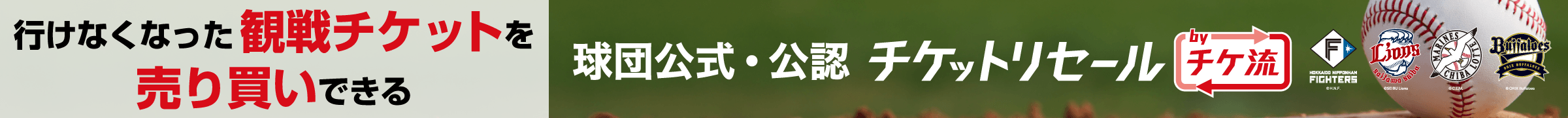先発完投から、リリーフをつぎ込む戦略へ変化
プロ野球の1シーズン当たりの完投数記録を見てみると、1位は別所昭投手(南海、1947年)で47完投と分業化が進んだ現代ではおおよそ考えられないような数字が残っている。トップの10人の中で1番最近の記録が1947年(別所、東急・白木義一郎=44完投、太陽・真田重蔵=42完投)にマークされたものであり、この記録を破るのはほぼ不可能だろう。
投球回でも、1位の林安夫投手(朝日、1942年)は1シーズンで541回1/3を記録している。こちらのトップ20で1番最近にできた記録は1961年(中日・権藤博=429回1/3、西鉄・稲尾和久=404回)。前述の完投数を聞くとだいぶ時間がたったように感じるが、それでも約半世紀前の出来事だ。
投手の起用事情は変化を続けている。半世紀前とは言わずとも、1989年に斎藤雅樹投手(巨人)が11試合連続完投を記録したような時代の先発完投主義の風潮はすっかりすたれてしまった。6人程度の先発投手が90~120球前後を目安に投げ、あとをリリーフ投手が引き継ぐ形が基本形になっている。
この変化はもっと短いスパンでも見ることができる。規定投球回到達人数、完投数、そして中継ぎ登板数という3点から、最近のNPBの投手起用の変化を見ていきたい。
まず、規定投球回到達人数。最近10年間の規定到達人数は平均27.9人。2018年で規定投球回を投げたピッチャーはセパ合わせて17人。2012年の33人から、年々減少が続いていて、2018年は過去10年間で最少となっている。
最多だったのは2009年で34人。セパそれぞれ17人の規定到達投手がいた。先発投手にとって規定を投げることの難易度が年々高くなっている。2015年までは、2014年を除き1人は200イニングを投げる投手がいたが、ここ3年間では2018年の菅野智之(巨人)のみとなっている。2010年には6人、2011年には7人の投手が200イニングを投げた。
中継ぎの登板数は増加傾向、メジャーでは「オープナー」という戦術も
最近10年間の規定投球回到達投手のセ・リーグ平均は14.3人、パ・リーグ平均は13.6人となっている。DH制を採用し、投手に代打を出されることのないパ・リーグのほうが、セ・リーグよりも長いイニングを投げやすいイメージがあるかもしれないが、規定到達者の人数ではむしろセ・リーグのほうが多かった。
次に完投数だ。最近10年間の完投数は平均116.6試合。2018年の完投数はセパ合わせて85試合にとどまった。2011年の168試合から年々減少が続いていて、2018年は過去10年間で最少の数となっている。最多だったのは2009年で172試合の完投があった。2018年は菅野が1人で10完投を記録したにも関わらず、最低の85試合となった。最近10年間の完投数のセ・リーグ平均は49.3試合、パ・リーグ平均は67.3試合。こちらはDH制を採用するパ・リーグと、採用しないセ・リーグの差が出ている。完投数でセ・リーグがパ・リーグを上回ったのは2015、16、18年の3年間ある。
最後に中継ぎ投手の登板数を見る。最近10年間の中継ぎ投手の登板数の総計の平均は2441.1試合、1球団当たりでは406.9試合となっている。1試合当たり約2.83人のリリーフ投手を使っていることになる。2018年に記録した数はセが2636試合、パが2619試合とどちらも最近10年で最多だった。最少だった2009年から増減を繰り返してはいるが、増加傾向にある。1シーズンでの中継ぎ投手の登板数が500試合以上だったのは、2011年の横浜(520試合)と2018年の横浜DeNA(503試合)のみだった。
最近10年間の中継ぎの登板数のセ・リーグ平均は2496.7試合、パ・リーグ平均は2392.1試合だった。DH制を採用しないセ・リーグは投手に代打を出すことが多く、それがこの数字につながっていると考えられる。パ・リーグがセ・リーグを上回った年は2015年のみだった。
日本でトップクラスの成績を残してきた先発投手たちが続々とメジャー移籍した影響もあるが、最近10年に限ってみても、NPBの継投策は、先発投手を引っ張らずに、早いイニングで多くのリリーフ投手をつぎ込む方向にシフトしている。MLBでは「オープナー」といって、初回からリリーフ投手を登板させ、短いスパンで投手を変えていく戦略も出てきた。今後、継投策はどのように変化していくのだろうか。
(Full-Count編集部)