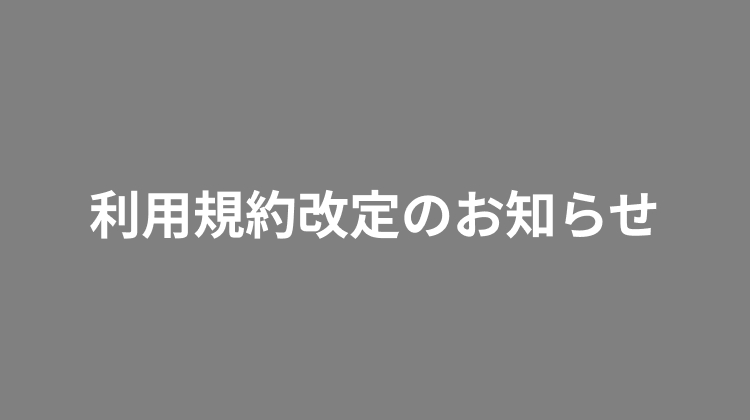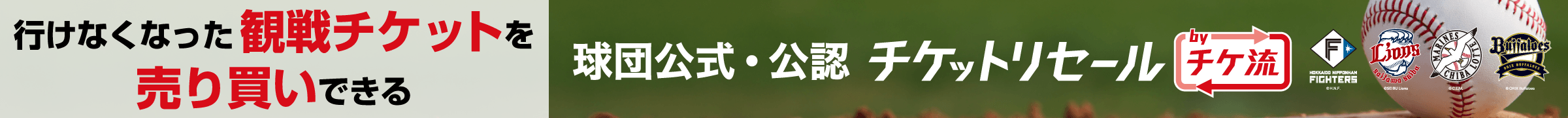4月17日、いよいよ楽天・田中将大投手が公式戦のマウンドに上がる。日本球界復帰が決まってから一挙一動に注目を集め続けた背番号18のピッチングは、2013年にシーズン24勝無敗と神懸かり、球団創設初の日本一を手繰り寄せた当時から、どのように移り変わっているだろうか。メジャーでの7年間で蓄積されたデータから、投球スタイルの変遷とともに、田中将の強みを3つ浮き彫りにする(※トラッキングデータ、および表データは「Baseball Savant」参照)。
メジャーでも指折りを証明した「制球力」
ヤンキースに入団した14年から昨季まで、メジャー通算78勝を挙げた田中将の投球内容を振り返ると、特筆すべきは「制球力」の高さだ。計173先発のうち57試合が無四球で、4四球以上を与えたのはわずか5試合だけ。通算与四球率1.78は9回平均で四球を2つ与えなかったことを示し、7年間で1000投球回に達した投手32人の3位に位置する。
通常、強打者揃いのメジャーに活躍の場を移した日本人投手は、三振を奪うペースはある程度維持しながら、四球を与える割合が増す傾向にある。だが、田中将は日米での通算奪三振率(8.47/8.46)とともに、与四球率(1.88/1.78)でもほぼ変わりがない。

ただし、渡米前後で防御率(2.30/3.74)の開きは小さくない。これは被本塁打率(0.45/1.36)の上昇が大きく響いた結果と考えられる。田中将が海を渡る前の数年間は飛距離が出にくい統一球導入の影響もあり、被弾は稀だった。それが、ヤンキースでの7年間は楽天での3倍以上まで上昇している。
メジャーでは、打者のパワーはもとより、田中将が海を渡った14年はリーグ全体が過渡期を迎えていた。10年台前半は「投高」に傾いていたが、15年からは本塁打の飛躍的な増加に伴い、投手全体の防御率も上昇傾向。ホームランが出やすいヤンキー・スタジアムを本拠地とした田中将は、17年にリーグワースト3位の35本塁打を浴びるなど、「打高」に転じる流れの憂き目に遭った。
日本人投手が必ずと言っていいほど直面する「メジャーの洗礼」。田中将の制球力をもってしても、そこは避けて通れなかったが、逆を言えば日本球界復帰により一発の脅威は薄れる可能性が高い。今年のオープン戦では3登板で3四球しか与えず、被弾も1本のみ。開幕直前に判明した右足の負傷は気掛かりだが、万全なら日米で冴えた制球が大きく乱れるとは考えられにくい。安定してゲームメイクする能力は、最も再現性が期待できそうだ。
縦に変化する「二枚刃」の切れ味
田中将の投球を紐解く上で肝心要なのが、決め球として用いた2球種の存在だ。メジャーでの7年間で田中将は、スライダーを全球種最多の4715球、次いでスプリッターを4372球投じた。通算被打率もスライダー(.196)がベストで、スプリッター(.207)とはワンツーだ。他4球種はいずれも3割台であるため、決め球のボールがいかに威力を発揮したか、積み重ねた数字が教えてくれる。ただ、近年はこの2球種の使い方に変化が起きていた点は見逃せない。
まず、海の向こうでもセンセーションを巻き起こしたスプリッターだが、ここ数年は落差が低下し、以前ほど空振りが奪えなくなっている。18年から縦の変化量(マウンドの高さ10インチを含む)は平均34.0インチ→31.9インチ→27.9インチと減る一方で、3年の間に約15センチも落差が失われた。その結果、空振りを奪う割合は36.2%→18.7%→23.0%とブレーキがかかっている。それでも低めに集めて、被打率は.210→.254→.207と大幅な上昇は避けているが、当時とイメージはやや異なるようだ。
昨季は短縮シーズンのため投球数自体が少なかったが、それ以前から田中将がスプリッターの落ち方に苦心する様子は何度も伝えられていた。もはや公然の秘密である非公式でのボール変更も影響したか、思い通りに操れなかったとの本人のコメントもあり、一過性の現象とは受け止められがたい。

一方、スライダーへの依存度は年々高まっている。投球割合は2年目から増え続け、昨季は37.7%にまで上った。スプリッターよりも縦の変化量が大きく、空振りを奪う割合は毎年安定して30%を超える上に、汎用性も高い。カッター気味に高速で小さく変化させたり、緩いスピードで大きく曲げたりと、その時々で自在に操っている。
直近2年はスライダーで最も多く三振を奪っている事実にも、この球種に対する田中将の信頼が透けて見える。球種別の奪三振数も、近年になってスライダー(383)がスプリッター(359)を追い越した。

今季、ここ一番の場面で田中将は、2つの決め球をどのように使い分けるだろうか。オープン戦で奪った13三振のうち、スライダーは6、スプリッターが2で、いずれも低めへ投じられたボールだった。使用球が変わって変化球の曲がりや落ち幅に影響があるかもしれないし、実戦ではバッテリーを組む捕手の判断や相手打者の力量も関係するだろう。
昨季のパ・リーグでは、スライダーに栗山巧(埼玉西武)が.333、柳田悠岐(福岡ソフトバンク)も打率.325と好成績を残し、フォークには吉田正尚(オリックス)が打率.449と破格の数値を記録している。チームの勝敗を左右するような場面では特に、リーグを代表する打者たちに対して、田中将が「二枚刃」をどう駆使するか見物だ。
攻め方の引き出しが増えた「投球術」
ピンストライプのユニフォームに身を包んでから、田中将は決め球以外にも微細な工夫を加え続けてきた。試行錯誤の足跡は、シーズンごとの球種別投球割合に表れている。
ヤンキースに移籍した当初の14年は、あらゆる持ち球を織り交ぜていた。翌15年はよりバランスが良くなり、全球種とも投球割合7.2%以上の配色グラフは7年間で最も均整がとれている。だが、最初の2シーズンとも4シームは被打率3割以上で、被本塁打は最も多く、明確に打ち込まれたボールだった。

対策として、16年には4シームの使用頻度を大幅に減らし、代わりに増えたシンカーは被打率.266で、被本塁打が3本のみ。結果として奪三振率は減ったが、リーグ3位の防御率3.07を記録するなど、キャリアベストの成績に結び付けている。
しかし、そのシンカーも、翌17年以降は被打率.340→.382→.375と捉えられてしまう。「バットに当てられると危険」。そうした認識が、「打高」化に向かうメジャー全体に浸透するなか、対抗策として潮流になった「高めへの4シーム」を田中将も採り入れた。

16年はほとんど投げなくなった4シームが17年に増え、18年からは毎年20%以上の割合で投げている。使用頻度だけを見ると最初の2年に立ち返った格好だが、投げ込んだコースは大きく違う。
1、2年目は右打者の外角と左打者の内角を軸に、全体へ散りばめるように配球していたが、近年は高め中心にはっきりとシフト。例えば、14年は高めのストライクゾーン外に44球しか投げていないが、19年は385球も投じている。使い方を変えてからも被打率は変わらず3割台を推移したが、空振りを奪う割合が上昇した。
直近3年間の田中将はスライダー、スプリッター、4シームの3球種を主体に投球している。19年は主要3球種だけで投球割合の9割が占められ、昨季も86.5%だった。そこに、浅いカウントではカーブでストライクを稼ぎ、バットの芯を外すために時折、シンカーやカッターを交えている。

メジャーでの取り組みが全て長期に実を結んだわけではないが、その過程で田中将は着実に投球のバリエーションを増やした。「投球術」に磨きがかかっている点は、未対戦の打者も増えている日本球界への再適応にもプラスに働くはずだ。
過去の傾向からピッチングの輪郭は浮かび上がるが、今季もそれらを踏襲するのか、今までとはガラッと違う攻め方も見られるのか。間もなく、マウンドの上で明らかになる。
文・藤原彬