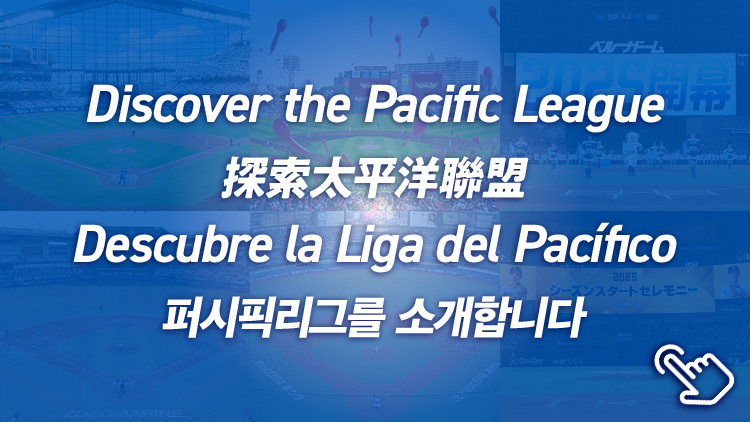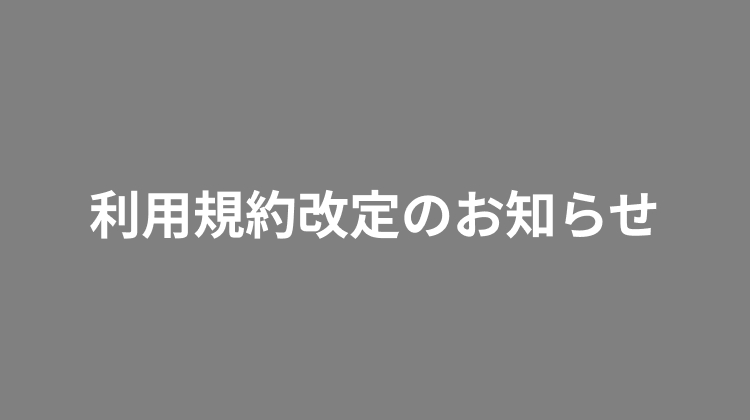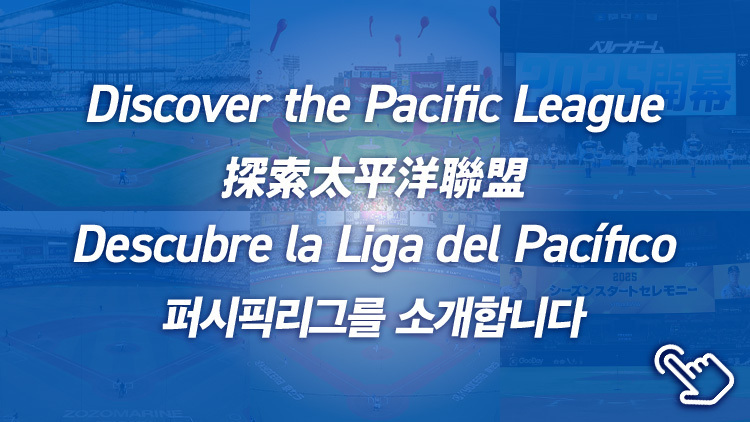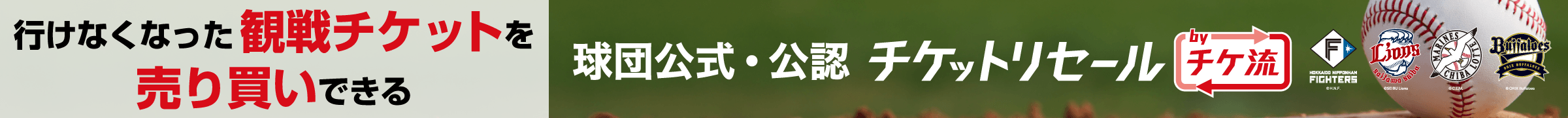パ・リーグはここ数年、積極的なプロモーションを仕掛け、台湾での日本プロ野球認知拡大を図っている。最近では台湾・台北で5月20日から23日に行われた台北国際観光博覧会(TTE)に出展し、日本の球場への来場を呼びかける活動を実施した。
パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティングは、FOXスポーツ台湾と2016年から3年間に渡る放映権契約を結んだ。そのため台湾ではパ・リーグ主催試合が年間260試合以上、1週間で換算すると10試合以上がFOXスポーツでライブ放映されている。先日私も台湾へ足を運んだ際には、野球の試合が身近な存在として扱われていた印象を受けた。実際、テレビではパ・リーグの試合が生中継されていたが、同時にメジャーリーグの試合も豊富に放映されていた。
台湾を始め海外への進出を図り、プロ野球としてもビジネスの拡大を目指しているが、その先を行くのがメジャーだろう。20年前はNPBと売り上げがさほど変わらなかったという数字もあるが、現在ではその差は何倍にも広がってしまった。
メジャーのリーグビジネス確立が間違いなくその理由の1つに来るだろうが、常に将来を見据えた海外への展開もその大きな要因となっているだろう。メジャーは今や233の国と地域で試合が放映されており、今季開幕時点では25人枠とインアクティブリスト(故障者リスト、リストリクテッドリスト)に入っている選手864人のうち、238人が外国人選手だった。その出身国・地域は18に及び、27.5%がアメリカ国外生まれの選手だった。
今年5月、残念ながらジカ熱の影響で中止となってしまったが、マイアミ・マーリンズとピッツバーグ・パイレーツの試合はプエルトリコで開催予定だった。プエルトリコは厳密に言えば、アメリカ合衆国の自治連邦区であるため海外とはならないが、メジャーは毎年のように海外でオープン戦や公式戦の開催を試みており、将来的な国外での球団数拡大、国際ドラフトの導入など、世界への発展が常に話題として上がっている。
また、メジャー主催で2006年にワールドベースボールクラシック(WBC)が始まったのは、メジャーの国際化をさらに進める大会としてもすでに認識されているが、2017年大会では予選から過去最多の国数が競い合い、本戦出場を目指した戦いを繰り広げている。
南アフリカのような国がWBCのような野球の世界大会に顔を出す要因を作ったのは、メジャーの海外進出の努力によるものだろう。2011年、メジャーは南アフリカのケープタウンにアカデミーを創設。このアカデミーはアフリカ大陸中から選手をスカウトし、メジャー組織で指導をするコーチたちの下で野球をするだけでなく、トレーニングや栄養学について学ぶ時間も設けられている。そして翌年には選手育成だけでなく、指導者向けのカンファレンスも開始した。「野球不毛の地」から選手を発掘するだけでなく、国全体の野球の底辺拡大と発展をサポートしている。
次世代育成のために実際アカデミーを作ることもあれば、2013年のシーズンオフには現役選手7人がさまざまな国へアンバサダーとして、各国で指導を行った。オランダ、フランス、中国、南アフリカ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドに選手たちが派遣されて、それぞれが指導をした。その中にはニューヨーク・メッツ所属のカーティス・グランダーソンやピッツバーグ・パイレーツの抑えを務めるマーク・メランソンなどの有力選手も含まれていた。
「サッカー王国」であるブラジルでも、2009年にはタンパベイ・レイズがメジャー球団としては初となるアカデミーへ投資することを発表した。そして2010年にはメジャーがナショナルトレーニングセンターを創設したことで、野球人口も少しずつではあるが増えていった。そしてブラジル人初のメジャーリーガー、ヤン・ゴームズが2012年にトロント・ブルージェイズでデビューし、ブラジル代表としても2013年WBCでパナマを破るなど、一気に躍進している。
ブラジルでは野球中継も増え、2015年時点では週に8試合ほど試合が放映されており、視聴率も2012年に比べる2倍に膨れ上がったという数字も出ていた。
さらに、南アフリカやブラジルだけでなく、世界各地で野球普及活動を広げていくことでメジャーというブランドも同時に浸透させてきている。活動する国で子供たちが野球に触れ、興味を持てば、自然とメジャー人気が高まる。するとグッズは売れ、需要が増えれば放映権料アップにも繋がってくる。そしてその舞台を目指す子供たちが世界から集結し、今シーズン開幕時には約30%がアメリカ国外生まれの選手が集うリーグにまでなったのだろう。この数字はマイナーリーガーも含めると、割合はさらに増すはずだ。
マイナーリーグの現場にいたこともあるが、アメリカにいるのかスペイン語圏の国にいるのか分からなくなってしまうほど、ロッカーではスペイン語が飛び交う。よく米国では人種・文化などの様々な異なった要素が融合・同化されている国として「Melting Pot(メルティング・ポット。直訳すると、るつぼ)」という表現が使われるが、それを凝縮しているのが野球界でもある。
ちなみに、2016年シーズン開幕前にはメジャーリーグ機構が各球団にスペイン語通訳を雇用することをルール化した。日本人選手にはメジャー契約を結んだ場合は必ずと言っていいほど通訳が付いているが、これまではスペイン語圏の選手にはほとんどの場合、指定された通訳は存在していなかった。各球団にスペイン語を喋る選手・コーチが多いため、必要性を感じていなかったようだが、メディア対応なども含めて通訳が必要という現場での訴えをリーグ側が汲み取り、新ルール導入となった。
島国である日本とアメリカの歴史を比較すれば、居住する人種に大きな差があるのは仕方がないことだろう。それでも多くの日本企業は海外へ進出を遂げており、野球大国の一つと言われる日本もさまざまな海外進出への活動を広げていくことで、さらなる可能性が広がるはずだ。
実際、千葉ロッテマリーンズで2002年から5年連続2桁勝利をマークし、アテネ五輪、そして第1回WBCにも日本代表の一員としてプレーした清水直行氏は現在、ニュージーランド野球連盟ゼネラルマネージャー補佐、そして同国の代表統括コーチを務めている。
メジャーの世界進出のスピードは緩まることはないだろうが、パ・リーグの台湾での活動、そして元選手たちが海外でプロ野球の輪を広げる取り組みを続けていくことで、日本のプロ野球を目指したいと思う子供たちも育てていくことが、今後のリーグ発展にも繋がるのではないだろうか。
パ・リーグもメジャーリーグも進める、野球の海外進出
パ・リーグ インサイト 新川諒
2016.6.18(土) 00:00