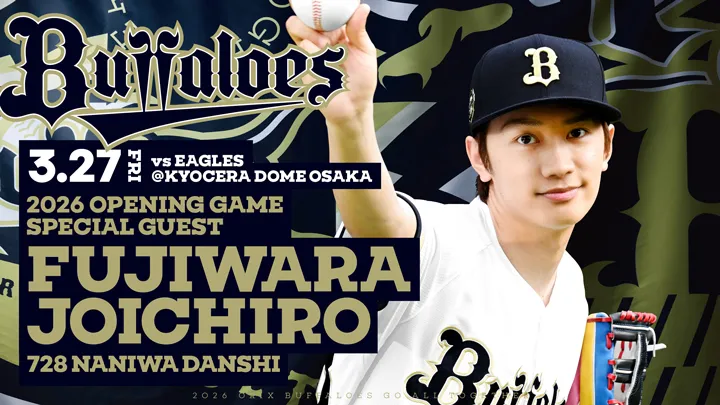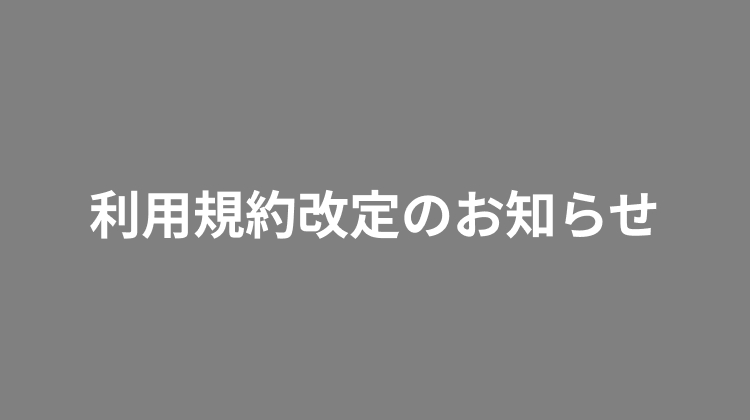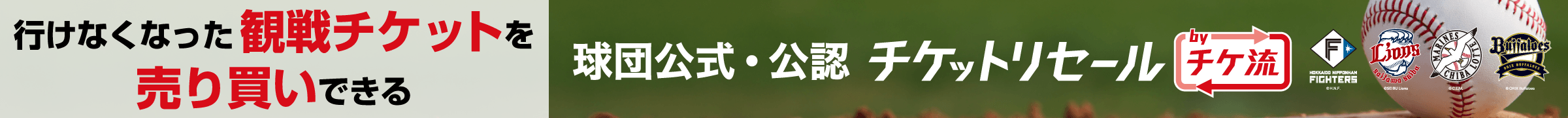敵地とはいえ、そこは地元だった。ドラフト1位ルーキーの平沢大河内野手が放った打球が中前に落ちると、アウェーとは思えぬ温かい拍手が沸き起こった。18歳の若者は1塁ベース上でちょっとホッとした表情で右手を上げて、声援に応えた。8月17日のイーグルス戦。生まれ故郷である杜の都・仙台でのプロ24打席目に記念すべき初ヒットは生まれた。
「正直、ホッとしました。本拠地のマリンで打ちたかったという思いもありましたが、宮城で打てたのは良かったと思います」
家族ら10人を試合に招待をして迎えた初めての仙台での一軍の舞台だった。仙台育英時代のチームメートも「応援に行くよ」と駆け付けてくれていた。入団前からのマリーンズファンの弟・大剛くん(中学一年生)はライトスタンドから声援を送っていた。母と一緒にスタンドから応援をしていたリトルリーグ時代からのチームメートの父親はその瞬間、涙を流した。ここまで一流のプロ投手の前で、なかなか自分のスイングをさせてもらうことができず、戸惑い苦しんだ若者は、奇しくも多くの知り合いが見守る前で記念すべき第一歩を踏み出すことができた幸せを静かに感じていた。
「早く、とにかく1本欲しいと思っていました。自分の中では焦ってはいなかったのですが、でも心のどこかでは早く打ちたいという気持ちがあった。祝福の連絡は結構、きましたね。高校時代のチームメートとはグループLINEがあるので、それを通して結構、きました」
故郷でのメモリアルな一打にふと野球と出会い、野球に打ち込み、心折れることなく、夢であるプロ野球を志した日々を思い返した。
13歳の時には東日本大震災を経験した。自宅が高台にあったこともあり津波の被害はなかったが、電気、ガスが止まった。時間の経過とともに被害の大きさが伝わるようになった。小学校時代に野球をした思い出のグラウンドは津波に飲み込まれ、跡形もなくなっていた。当時、所属していた中学野球チームの仲間たちも被害にあっていた。自宅が浸水して野球用具が使えなくなった選手や、家が流された選手たちがいた。練習グラウンドに隣接をして仮設住宅が立った。チームは消滅の危機となった。保護者たちは約1か月、話し合いを続けた。野球をやっている場合なのかという意見も出た中、自宅を流された家庭の保護者が頭を下げた。「子供たちには野球を続けさせてあげてほしい」。心からの願いだった。その一言で決まった。チームは消滅の危機を乗り越え、平沢も野球を続けることができた。
「チーム全員で被災した方のためにという思いが強かった。そういう力は大きかったと思う。震災前まではただ野球をやっている感じだったけど、野球をしたくてもできない人がいる。あれから、そういうことを理解して自分の環境に感謝するようになった」
練習に向かうため、仮設住宅の前を通りかかると「野球、頑張ってね」と声をかけてもらった。自分よりも大変な想いをしている人から声を掛けてもらえることが励みになった。平沢が所属していた中学野球チームはその人たちの想いを背負ってその年、夏の全国大会に出場。悲願の全国大会チーム初勝利を挙げた。みんなの野球への想い、そして被災した人たちへの気持ちが、不思議な力を引き出してくれたように感じた。それは今まで味わったことのない感覚だった。だから、仙台育英高校に進学が決まった時も東北のために、甲子園優勝を目標に掲げた。
「周りは意識をしていない人もいたかもしれないけど、自分はずっと東北のチームが優勝をしていないのを知っていたので、東北に優勝旗をと、入学前から考えていました。特に高3夏の大会は決勝までに岩手代表の花巻東高校、秋田代表の秋田商業を破って、勝ち進んだこともあり、それら東北勢のためにも勝ちたいと強く想い、気合が入りました。東北に優勝旗を持って帰りたいという気持ちが強かった」
想いは残念ながら実現はされなかった。決勝で小笠原投手(現ドラゴンズ)擁する東海大相模高校に敗れ、準優勝。悔しさを胸に仙台駅に戻ると見たこともないような人だかりがあった。構内にも外も仙台育英ナインを見ようと人が集まっていた。「感動をありがとう」と声をかけてもらった。その時、自分の想いが、野球のプレーを通じて伝わっていたことに気が付いた。その時に決めた。プロ入りをして、もっともっと野球を通じて、人の心を動かせるようなプレーをしたい。そして一つの縁から千葉ロッテマリーンズに入団をし、背番号「13」を身にまとった。
2月28日。平沢は母校の卒業式出席のため仙台育英高校にいた。式終了後、3年生全員でいつも汗を流した室内練習場に集まった。それぞれが違う道を歩む。大学で野球を続けるもの、野球はせずに新たな目標を目指すもの、いろいろな夢が広がっていた。野球は止め、消防士を目指す仲間たちがいた。社会の役に立ちたいと大志を抱く仲間たちの想いが胸を熱くさせた。だからこそ、自分はプロ野球選手として、夢を伝える役割を全うすることを誓った。だから、プロの壁にぶち当たっても、弱音を吐かなかった。5月に初昇格も、快音を奏でることなくわずか10日で抹消。一軍のスター投手たちの前に、手も足も出ずに凡打を繰り返した。二軍に戻ると、強いスイングを意識し打撃練習を繰り返した。朝から夜までスイングを繰り返した、遊び盛りの18歳は休日もほとんど寮を出ることなく、野球に打ち込んだ。
それでも、不安にさいなまれることはあった。そんな時は高3夏の県大会を前に仙台育英高校の佐々木順一朗監督の言葉を思い出した。それはもし最後の夏に県大会で敗れ、甲子園に行けなかったらどうしようという当時、思い描いていた不安を力に変えてくれたメッセージだった。
「不安がなかったら、人は頑張れないぞ。不安があるから、努力をする。成長をしようとする。今、不安を抱えているのなら大丈夫。きっとうまくいくよ」
周りはマリーンズを背負う逸材と褒め称えてくれる。時にはそれが重荷に感じることだってある。そんな不安な思い、一軍での挫折、プロ野球選手としての大志が平沢を奮い立たせた。
初ヒットをキッカケになにかが変わった。17日から21日まで5試合連続安打。20日のライオンズ戦(西武プリンスドーム)では、本塁打まであと少しというフェンス直撃のプロ初適時打を放った。「1本出て、気持ちが楽になったのかもしれない。余裕が出てきたと思う」と手ごたえを口にした。今シーズンは残り30試合。残された舞台は少ないが、そこで2年目に向けた確かな感触を残し、首脳陣にアピールすべく毎日を必死に過ごす決意だ。
「一日一日を大切に、目標を持って過ごしていきたい。うまくいかないことも多いけど、それをしっかりと受け入れて前に進んで、その結果として勇気を与えられるようなプレーができればと思う」
将来を渇望される大型内野手が今、プロの第一歩を踏み出し、歩みを始めた。その物語が今後、どのような展開が待っているのかは誰も分からない。ただ、そのプレーを通じて、感動を伝えたいという大志を持つ若者が作り出す物語はきっと我々の想像を超える、素晴らしいストーリーとなるに違いない。時には山あり谷あり。それを乗り越え、成長し、マリーンズをけん引する存在となるはずだ。