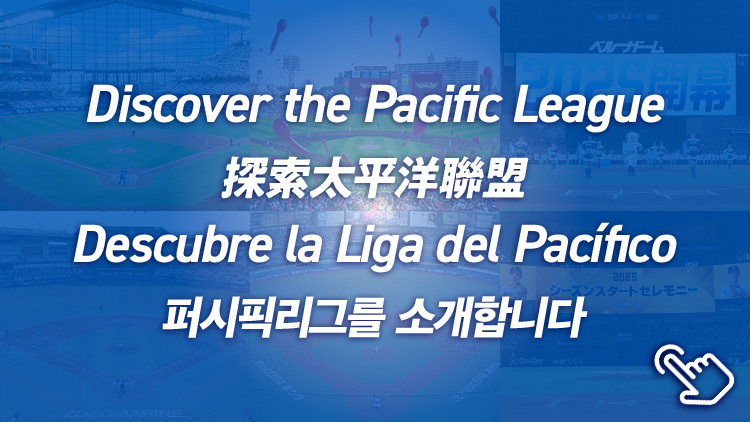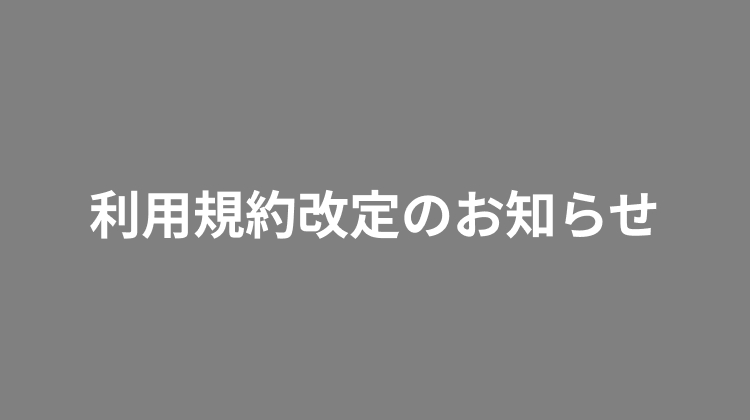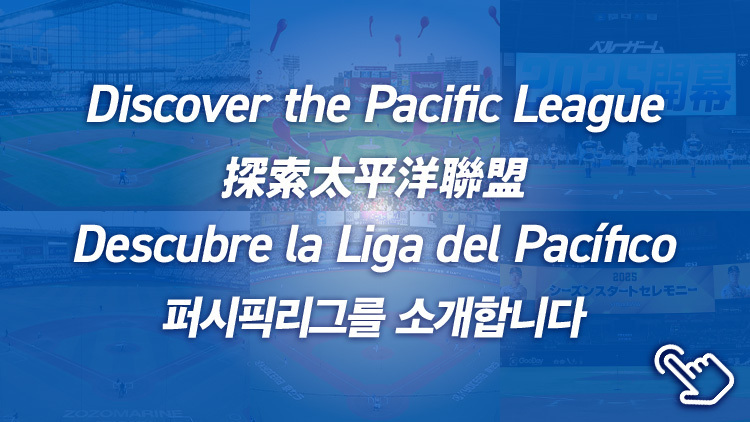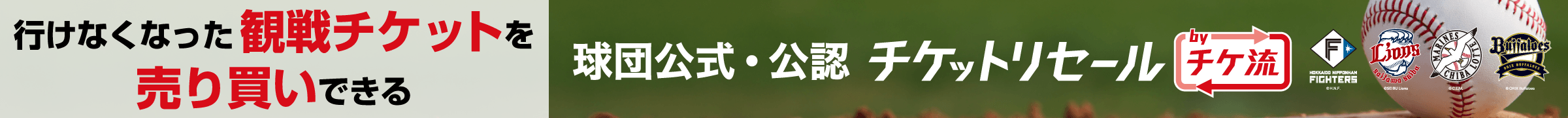外国に行くとき、あなたは何を心配するだろうか? 財布を盗られたらどうしよう? 事件に巻き込まれたらどうしよう?
一方で、オリンピック招致プレゼンでも紹介されていたように、日本は落とした財布が警察に行けばほとんどが返ってくるような安全な国だ。24時間開いているコンビ二やレストランがどこにでもあり、外国人にとってはあまりにも便利で、生活しやすい面があるかもしれない。
それでも、コミュニケーションツールや表現の違い、恋しくなる自国の慣れ親しんだ食事、そして様々な生活基準の違い、などなど、彼らが日本で「快適」に住むにはいくつもの壁がある。
命の危険と常に隣り合わせの国から、安全で知られる日本へやってくる外国人選手。そして、自ら日本を出て、危険と知りながら他国へ挑戦する選手。私はロチェスターで仕事をしていたとき、試合後ホテルへ1人で帰ろうとすると、当時の監督に言われた言葉がとても印象に残っている。
「1人では絶対に歩いて帰るな」
何年も前、在籍選手が1人でホテルへ戻る時、事件に巻き込まれそうなことがあったそうだ。それ以来、チームでは危険な場面に選手が直面しないよう、数人で行動するように促していた。
通訳の難しさは「空気感の違い」
海外で挑戦する動機はそれぞれだが、外国で直面する苦悩やカルチャーショックは、誰しもが一度は経験するのではないだろうか。海外へ行くとき、一番困るであろう「コミュニケーション」だが、これは単に言語だけに限らない。それぞれに文化の違いがあり、特にメジャーリーグのように、多様な人種・文化が混在する国ではアメリカだけでなく、ラテン系の文化も理解することがキーポイントとなる。
通訳をしていて顕著にそれを感じたのはミーティングのとき。言葉では表しきれない全体的な空気感の違いを感じ、単に「言葉を訳す」だけでは伝わらない。一番難しかったのがアメリカ人特有のジョークを訳すことだった。ミーティングで監督やチームメートたちは、よく有名なドラマやコメディの決まり文句やジョークを使う。
それを知っているかどうかはアメリカ人でさえ個人差があるのに、表現を直訳しても、担当していた日本人選手には伝わらないことがほとんどだ。長々と説明している間に、ミーティングの話題は本題にいってしまうのだ。もっと何か工夫ができれば…と自分の力不足を感じ、当時担当していた選手らには申し訳ない気持ちも未だにある。
「カンガルー・コート」とは?
そしてクラブハウスの中では、「カンガルー・コート」というしきたりがある。カンガルー・コートとは、チームメートの行動や振る舞いを糾弾し、それを裁判に見立て、皆で有罪無罪を決める。長いシーズン中、選手同士が冗談を交えながらの反省会をするのである。
その「意見箱」は、クラブハウスに設置されており、チームの若手にはそれをわざわざ各遠征地へ運ぶという役割がある。意外に米国の地でも、後輩が荷物を運ぶといった上下関係があるのだなあと思う場面だった。
この「カンガルー・コート」も、選手間でのコミュニケーションを促す意図があるわけだが、いろいろなジョークが飛び交い、なかなか仲間に入るには困難な時間である。私の義父が、ニューヨーク・ヤンキースのファンタジーキャンプ(MLB球団主催で誰でもメジャーリーガーの気分を味わえることができる、大人のためのベースボールキャンプ)に参加したことがあり、その時にもカンガルー・コートが開かれた。わけも分からぬまま皆の前に立たされ、罰金を払わされたというエピソードを聞いた。
食事の苦労
食事も適応できるかのポイントだろう。日本でも多くの多国籍レストランが展開されているのと同様に、米国では日本食がブームとなり、日本食レストランが各州で見つけられるようになった。しかし、それらは「懐かしい味」とは程遠い。
問題は試合後の食事だ。米国ではクラブハウスで食事が用意されているが、場所によってその質は異なる。日本ではホテルに戻って、食事会場が用意されているだけではなく、街に出れば夜遅くまで飲食店は開いている。しかし米国ではほとんどのレストランは有無を言わせず夜10時ごろに閉店する。唯一朝2時まで開いているスポーツバーでは満足できる食事は期待できない。
ある球場のクラブハウスで遠征チーム担当のクラビー(クラブハウス職員)が、我々日本人にご飯を炊いてくれたことがあった。少しでも懐かしい味を提供してあげたいという心遣いだった。しかし、残念ながらこのご飯がとてつもなく臭かったのだ。この球場スタッフへの感謝と彼らの名誉のために詳細は触れないが、日米で作ってもさほど変わりないと思われる白飯でさえ、日本人が食べられる味にはできなかったのだ。
「オフ」の過ごし方が適応の鍵?
球場で過ごす時間が多いメジャーリーガーではあるが、シーズン中最も重要なのは「オフ」の過ごし方かもしれない。オンとオフの切り替えが重要だとよく言われるが、例えば日本にいれば、お風呂に浸かったり、友人と食事に行ったり、ストレス解消方法の選択肢はさまざま。やりたいことが多すぎて時間が足りないに違いない。
しかし、米国には大きな体をしっかりと休められる浴槽などなく、心の底から楽しむことができる友人も少ない。むしろ時間を持て余してしまう場面が数多くある。野球という「仕事」をするために、そして自身の挑戦のために海外へ渡り、多額な年俸をもらうのであれば仕方がないという見方もあるかもしれない。しかしこの問題は万人共通。どれだけ高額の受け入れ体制が整っていても、誰しも慣れない環境へ行けば、普段の生活やオフの過ごし方に悩み、そこにストレスを感じれば自然とパフォーマンスも落ちてしまう。
「ベースボール」は世界共通の言語とはよく言われる。それでも国によって細かな決まりがあり、そこには暗黙のルールも存在する。球団、監督が変わるだけで1つの投球や打撃に求められる真意が変わる。それが国を越えるとなれば…皆さんも想像できるのではないか。選手には大きな戸惑いが出る。
フィールド上での様々な苦悩は当然のこと。その苦悩を打ち破らない限り、「勝てない」ことは周りがとやかく言うより、本人たちが一番理解している。そして何より彼らはそれを打破できるレベルに達したプロでもあるはずだ。しかしながら、フィールドを出れば一人で仕事に来た普通の「外国人」であることを理解してほしい。
コンフォート・ゾーン(慣れ親しんだ環境)を捨て、海外へチャレンジする外国人選手がいることで、我々の世界が広がる。成功・失敗と結果だけで評価するのではなく、彼らが経験する苦悩や文化の違いを少しでも理解し、サポートする側もそれを支え、今後より多くのアスリートが世界を目指せる環境作りに徹していければと思う。