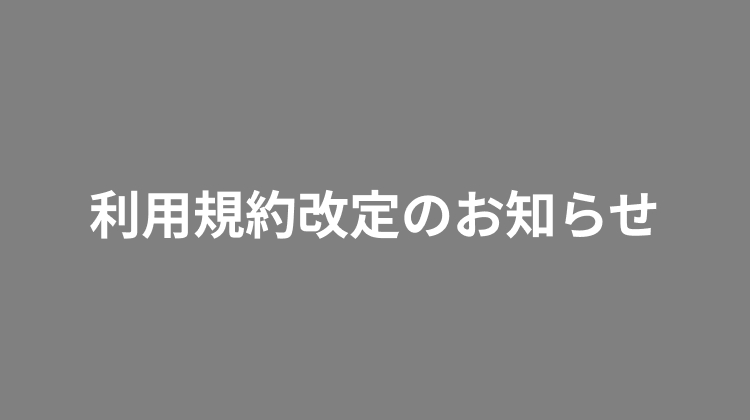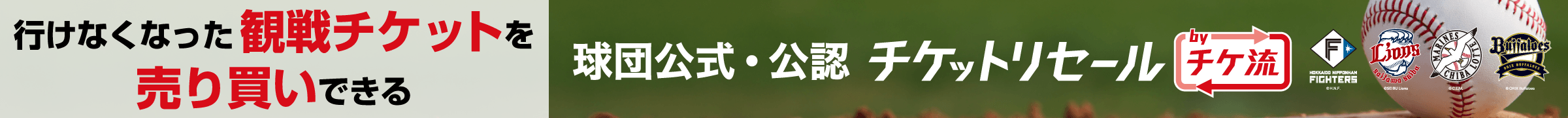プロ野球のグラウンドを離れて3年が経っても「生涯現役」の信念を曲げることはない。中村紀洋氏は現在、Ns methodで野球の指導に携わることでチャレンジを続けている。「ヤフオクドームは狭くなったね。あんなの楽勝ですよ」と笑う大阪が生んだホームランバッターは、広い大阪ドームやナゴヤドームを本拠地にしても、お構いなしにスタンドの最深部へホームランを突き刺し続けた。インタビュー前編では、シグネチャーであるフルスイングの哲学から大阪近鉄のリーグ制覇、中日での日本一など、実働22年に渡る激動のプロ野球生活について振り返ってもらう。
「ホームランの打ちそこないがヒット」の真理
「初球からは打たない。真っすぐやったら『1、2、3』で打てて面白くないからね」
プロ野球歴代17位となる通算404ホーマーを放った中村紀洋氏にとって、豪快なスイングから繰り出されるホームランが代名詞であることに異論の余地はない。そのキャリアで、個性派選手によって彩られてきたパ・リーグの顔として、数多の強打者を輩出した“いてまえ打線”の象徴として、見事なバット投げや派手な風貌でもファンを大いに楽しませた。だが、それらはすべて真実であっても、野球選手・中村紀洋のすべてではない。
「チャンスになったら、それまで見逃していた初球のボールをカーンと打ちます。相手は『見逃していたのに』となりますよね。そこはデータが頭の中にある。ピッチャーの心理を考えても、こういう場面ではほとんどストライクゾーンにボールが来ます。ただフルスイングをしただけでは打てないので、予告先発が発表されたら、夜も寝ずにその投手のビデオを見て、イメージしながら全部整理しておきます。前の状況を少し書いておけば、次にバットを構えて相手を見た時にその内容を思い出します。文字を書くことによって『来た!』と身体が勝手に反応するようになります」
狙ったボールをしっかりと見極めて好球必打――。「豪快」なスイングを可能にしたのは、「緻密」な下準備と「慎重」な姿勢だった。一軍に定着した3年目の1994年から毎年、相手投手に投げさせた球数は1打席平均で4球以上。規定打席に到達した15シーズンのうち、1打席あたりの平均被投球数でリーグ上位5傑に名を連ねること13度、1999年からは6年連続で最多だった。
「そうやって頭を使っていたわけです。『100%こういうボールが来る』と仮定して、フルスイングをしました。闇雲には振っていないです。来た球を打てと言われても絶対無理ですから、頭の中で構想を立てる。レギュラーになってからは考えないと。1試合に4打席回るから、フォアボールが1つとれたら3の1でいい。終わってみれば打率3割3分3厘で凄いバッターです。調子の悪い日はフォアボールを2つ選べば、打率も上がってくる」
「実力のパ」を生き抜くには18.44m間の駆け引きを制する、したたかさが必要だった。きちんと振り切ったからこそ、ポテンヒットや内野安打になった打球もある。「ホームランの打ち損ないがヒット」と豪語していたのは、裏を返せば、狙わなければオーバーフェンスしなかったからだ。「だから、僕の感覚では『ヒットの延長がホームラン』とはならないです」と中村氏は語る。狙いとフルスイングが一致して初めて、驚弾が炸裂した。
大阪近鉄のパ・リーグ制覇と中日の日本一に貢献
「何かを起こしてやろうと思っていました。心の中ではね」
中村氏が一軍に定着してからの近鉄・大阪近鉄は下位に低迷したが、2001年は夏場に首位争いを繰り広げた。9月3日からの対西武3連戦をすべて落とし、パ・リーグは上位3チームが0.5ゲーム差以内にひしめく大混戦に。首位攻防戦での全敗にチームメイトは肩を落としたが、中村氏が気落ちすることはなかった。先を睨み、次の3連戦で3勝すればいいと、そのバッティングと同様に裏付けを作ったからだ。
「本当に弱かったから野次られることもありましたけど、観に来てくれるのは気になっているからです。その人たちをいつか笑顔にしたいと思って野球をしていました。最下位の時にキャプテンでしたから。言葉だけじゃなく、成績を残さない限りは誰もついてこないと思って、チームのためを考えながら」
不言実行。前年の39本塁打、110打点での二冠獲得に続き、46本塁打、132打点の打棒で、12年ぶりとなるリーグ優勝を果たしたチームの原動力となった。だが、球団4度目の日本シリーズに挑戦しても悲願は成就されず。「日本一になれない球団のまま終わってしまいましたけど、それが決められた運命だったのかな」と、当時を振り返る表情に侘しさを滲ませる。その後、中村氏はプロ野球球界再編をきっかけにメジャーリーグへ挑戦。1年後に日本球界へ復帰すると、中日と育成契約を結んだ2007年に日本一の頂に立った。
「中日ドラゴンズで日本一になれましたけど、よそ者が入ってきてレギュラーになって、ファンの人の気持ちはどうなのかなと。ファンを意識しながらプレーした1年だったので、53年ぶりの日本一で恩返しするつもりでした。あの時は、自分の役割を考えながらやっていたチームなので強かった。一人ひとりが考えられる選手が9人集まれば絶対勝てますから。それは究極ですね」
猛烈な勢いでパ・リーグを制した大阪近鉄に対して、地に足がつく成熟した野球を売りとするのが中日だった。異なる強さを体感した中村氏はその後、求められる場所を探して他球団を渡り歩く。
プロフェッショナリズムを追求した先に訪れた人生の転機で、最後は「義」を選択
「好きなことを仕事にするのは贅沢な話ですけど、一生それでは食えません。プロ野球で活躍できる平均年数が7、8年なら、高卒の選手はいくつまでという話です。だから死に物狂いで、できるところまでやったろうと思って。クビと言われても何とかしようと転々としたわけです」
個人タイトルの数々とチームの栄光。プロ野球人生で多くを手にした一方、辛酸もなめた。だが、実力勝負の厳しさこそプロの世界なのだと言い切る。
「今のプロ野球の環境では給料をある程度に抑えられて、それで誰がやる気を出すのかと思います。アメリカなら、やればやるほど給料は上がって、その代わりできなかったらすぐにクビを切られる。それがプロです。そういう感覚が日本は遅れていると思います」
プロ野球選手が個人事業主であるという考えに沿えば、理想とする環境や条件を求めるのはあるべき姿だ。それにそぐう実績を残したのだから、選択肢も増える。迷いも生まれた。その姿勢や真意が伝わり切らずに、自分本位と報じられることもあった。「日本は人と人ですから。言いたいことを言うと嫌われます。日本人は情が入りますけど、感情が入ると交渉になりません。アメリカはそんな感覚がないので成り立ちます」。
実力の世界で成り上がった中村氏が、主張しなければ埋もれてしまうアメリカでのプレーを志したのは当然かもしれない。それでも、情の存在自体を「日本の良さ」として否定することはなかった。2002年にFAとなった際、メジャーリーグ挑戦を心に決めたが、最後は当時の梨田昌孝監督の言葉で翻意して大阪近鉄に残留している。
「あの時の過酷な人生は今の生活にも生きているし、感謝しています。今考えればビジネスで動けばよかったと思いますけど。『世の中、金なんかな』と思うこともありますよ。でも、やっぱり日本人だから情じゃないかな。礼には礼で返す。恩を仇で返すなんて絶対に無理ですから。何かしたら何か返すのが日本人。もう、そんな経験はしたくないですけどね」
野球だけではなく、自らの職業観と真摯に向き合った。それゆえ、当時の葛藤や苦悩の記憶は、今もリアルな感情とともに脳裏へと深く刻み込まれている。
猛者でひしめく時代から得た教訓を、現在の野球指導に生かす
「『これで大丈夫なの?』『今やったらアウトやな』ということが多々あった(笑)。当時は凄かったですからね。でも、そういう時代もあって楽しかった」
現在ほどルールの締めつけが厳しくなかった当時を「今なら笑い話、思い出にもできる」と懐かしむが、一筋縄では行かない時代は熾烈だった。
「今の若い選手がどうかは分からないですけど、僕たちの時代は『上のもんを蹴落としてレギュラーをとれ』。ライバルが風邪を引いたり、怪我をしたら『よしっ』て、皆が言っていました。プロ野球選手だから、ポジションがなかったら何のためにいるのか分からない。『デッドボールを食らえ』とか『フォアボールを出せ』と昔は味方が思っていましたね。今はもう、そんなことはないと思う」
当時のプロ野球界に豪傑エピソードは事欠かない。コンプライアンスが今ほど強調される時代ではなかったからこその、おおらかさがあった。その間隙で発生する「滅茶苦茶」が、否応なく選手に対応力を身に付けさせた側面もあったはずだ。中村氏は指導を続けるなかで、現代の子供に「イメージする力」が不足していることを指摘している。では、イマジネーションはどう養えばいいのだろうか。
「先を読んだらいいと思いますね。先を読めるように、その土台を作ればいい。どうなるのかを先に読んで、そこに向かってイメージした物を追いかける。仮想のものを追いかけても駄目だけど、子供たちならプロ野球選手になるにはどうすればいいかをイメージする」
達成イメージからの逆算は、打撃で結果を残すための方法論と同じ考え方だ。そこで、重要なのが「かみ砕く作業」となる。
「現役当初から色々な指導者の下でやってきて、様々な指導を受けました。それをそのまま中学生、高校生に教えても分からないと思います。現役時代から指導者に教わったことを簡単な方法にして取り組んでいたからこそ、今も『こうしたら子供たちにも分かりやすい』と考えられる。だから、今は何を聞かれても全部答えられます」
指導に話題が及ぶと、中村氏の口調は一層熱を増した。
(後編へ続く)